
今回は、三保通信ご寄稿者とご講読者お三人展と、加えて社長出張時(2/27・28・29)長崎・平戸の生月島(いきつきしま)「島の博物館・島の館」(長崎県平戸市生月島)にて求めた瀬崎正人さんのイラスト画入り葉書を展示しました。

岡田さんは、いつも三保通信にイラスト画をご寄画頂いています。

S.Kさんは、ご講読頂くとともにイラスト画をご寄画頂いております。

Asukeさんはご寄稿とともにイラスト画でもご寄画下さっています。

社長が、久留米・熊本・長崎を出張にて訪れた折、長崎・平戸市の生月島をご案内頂き、瀬崎正人さんのイラスト画に巡り会いました。
瀬崎正人さん
1958.8.9 広島県江田島に生まれる。3歳で長崎県佐世保市に転居 (昭和33年) 1974.4 佐世保工業高等学校入学。
九州の北西端に位置する平戸市生月島は、かくれキリシタンや古式捕鯨などの貴重な歴史文化を有しており、博物館はこれらを紹介する施設として平成7年に開館。展示スペースは、「勇魚とりの物語(捕鯨)」「島の暮らし(民俗)」「かくれキリシタン」「シーファンタジックアリーナ」の常設コーナーのほか、企画展や絵画展を行う企画展示室がある。(平戸観光協会)

写真は拡大していて、残っている竹が近くに見えますが、実は結構高いところに在ります。下まで下ろすには中々苦労します。本当は竹の下の方(太い方、欲しい葉っぱの方は上で、、)から斜面を下ろしたいのですが、、私のような素人は苦労します。葉っぱが付いている上の方が先になってしまうと竹の木は滑り降りてくれません。
竹は隣家の農家さんが「持ってっていいよ」と言ってくれて、それで貰っています。

これが、滑り下ろした竹の木から、枝葉だけ切り取っているところです。

切り取った枝葉をチッパーで〝竹チップ〟にするところです。この機械はもう30年位使っていて、私にとっては愛着のある機械です。つい最近、初めてオーバーホールしました。メーカーさんが三島市にあって、直接持ち込みました。持ち込んでから3週間くらいしてから、オーバーホールが完了しもう一度三島に取りにいきました。もうこの機械は生産していなくて、部品がないところを何とか用意したとのことでした。お陰ですごく調子良くなりました。歯も新品同様に研いでくれました。

出来た竹チップを畑に鋤き込みます。チップが後になったときは畝間に敷いておいて、チップが土に馴染んできたところで畝に鋤(す)き込みます。ほとんど、チップが自分で土になじんでいくように見えますが。

竹チップは、「草でもない木でもない」と言われて、土に還り易く土を腐敗させにくいといわれます。竹チップは、まさにリサイクルです。山は至る所で竹林が威勢よく、筍(たけのこ)収穫をしなければ竹林はその勢いで杉・ヒノキの間に伸びて杉は負けていきます。この竹の太い方も出来るだけリサイクルします。しかし今は、稲を干す用の竹にも使われず、竹細工もプラスチックがそれに取って代わりました。次の写真の肥料場の囲いはこの太い竹を応用して使っています。

こちらは生ゴミの衣装ケースでのリサイクル方法(第一段階)ですが、ケースに入れて敷くボカシも自作です、ボカシで生ゴミは全部肥料になります。出来上がれば、この肥料場に開けて(第二段階)さらに草チップや枝チップ、灰(少し)などとともに時間を掛けて肥料になっていきます。ただ、カブト虫が繁殖してしまうと、ちょっと困りものです。カブト虫の幼虫が巣立ってしまえばいいのですが、時折撹拌したいのでそれで困ります。竹チップに、この肥料場の肥料も入れますが、ほとんど竹チップです。畑ではケール(青汁用)を2年作りました。成績はいいです。
今は花をつけていません(呼び名は「シャガ」のようです、、)が、あれっ、首を振っている、、?! 何してんだろう?と思ったんです。しきりにこちらを呼んでいるように、。

ところは、林道散歩の第2の名所、それはこの紅葉(もみじ)の木のある所です。

もみじの木、こちらは正面の顔、、

こっちが横顔です。「こちらを呼んでいる」というのは、一瞬私が、もみじになってしまっていますがそれは違います。いつも一緒にいるモミジがそう思ったのだろう、、と。

何に見えるでしょう、?アンテナか、?
モミジの木が、シャガの‶振り〟を見て、どっちがどっちか分かりませんが、相呼応しているように思いました。
林道なくしてこの光景も見れないのですが、林道以前からの長~い、その自然の営みに、むしろ生きているが故の想像をさせてもらっています。これも山間ならではの恵みなのではないかと心和ませてもらっています。
追伸
シャガ(射干)は、アヤメ科アヤメ属の多年草です。5月以降に咲くイメージのあるアヤメ科の花ですが、その中でも先陣を切って花を咲かせるのが「シャガ(射干)」の花です。北海道、沖縄以外の本州全体に分布し、森林周辺の木陰や山地など、やや湿ったところに自生、群生します。学名の種小名に「japonica(日本の)」とついていますが、実際は中国原産で帰化植物です。(SAIYU TRAVEL CO.,LTD.ブログ「西遊旅行」より)
第2の名所はもみじ(紅葉)の木ですが、第1は岩場の椿、第3は桂の木、第4は河原、そして第5は春さんの竹林です。わたしが勝手につけた‶名所〟ですが、長~く生きてきているそれらに不遜極まりないですが、一時の楽しみとさせて頂いております。
皆様に置かれましても、くれぐれもご自愛お過ごし頂けます様お願い申し上げます。
カテゴリ
プロフィール
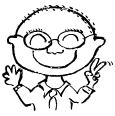
- 花澤 久元
-
- 誕生日:1946年11月6日
- 血液型:O型(Rh+)
- 趣味:スイマグ造り卒業、もっか青汁作り
- 自己紹介:
母親に首根っこつかまれて飲んでいたスイマグとの付き合いも早70年。
起きがけのスイマグ飲用を忘れず、青汁作りに精を出し、夕食を待ちこがれる”マイナス腸活”を楽しんでいる。

